養蜂場の跡地に養鶏をしたい。
閑散とした養蜂場跡地を眺めながら思いました。

自分で育てたニワトリから美味しい卵を採りたい。
そして美味しく食べたい。
何よりミナグ君と一緒に卵を孵化させてヒヨコを育てて命の大切さなどを身をもって体験させたい。
思いついたらすぐやりたくなります。
コンセプト【作るなら美しい物を】
いつものコンセプトで今回も頑張ります。
イメージがわかないのでとりあえずブロックを並べて大きさを確認してみました。

建てる小屋の面積を決める。
大きさを決めるのに色々検討。
飼う鶏の数によっても違うとは思うのですがとりあえず1坪。 いや建てるなら2坪。
悩んだので1.5坪で決定。 1間×1.5間=1.5坪
畳3畳の計画としました。
平均的に一坪に約10羽くらいが目安だそうです。
早速『遣り方』を立てて水糸を引いて位置を確定しました。

基礎をコンクリートブロックで作る為にラインを出します。
私は建築士なので建築工事はお手の物
今回は私一人で建てる予定です。
レベルと通り芯、直角をレーザーで確認。
こういう機械があるので一人でもなんとかなります。
通り芯に受光機を置いて手前でカネを振ります。(カネとは直角を出す作業のこと)

鶏小屋基礎工事
ブロックのレベルを出すため鍬で土を掘り、から練りのモルタルでブロックを設置。
ひとつひとつ確認しながら地味に作業を進めます。
なんか体を動かしながら熱中するのって楽しい。

ひと通り並べたらブロックにモルタルを充填して基礎として強度を確保します。
アンカーボルトも埋め込み完了です。

ブロックの隙間にモルタルを充填して基礎工事の完了。
鳥小屋の床は発酵床としたいのでこのままで土を入れる予定です。

壁を建て込む前に内部に土を入れました。
みなぐ君もちょっとお手伝い。

壁工法で建て込み開始
パネル工法として24mmの構造用合板を壁として建て込んでいきます。
最初に2枚を一人で建てるのに苦戦。
一人で建ててもう一枚を持ってこないと組みあがらず一人作業に困惑しました。
知恵を絞り何とかなりました( ´艸`)

二枚を立てれたら後は簡単です。
何とか四隅を固める事が出来ました。

前面は、大きく開けて開放的な鶏小屋とします。
後は風の流れを入れる為東面の一部と扉部分に開口部を持ってくる予定です。
北面は風を避けるために開口部は作りません。

前面の大きな開口部に網を張る予定でしたがマチジョさんが頑丈なエキスパンドメタルを提供してくれました。

網だと破られる恐れもあるけどエキスパンドメタルなら全く心配ありません。

鶏小屋の塗装工事
壁工法として24mmの合板を使っているので塗装を行います。
合板自体は、強度はあるけど水には弱く常に風雨にさらされると劣化が進みます。
防水対策として全面を塗装しました。

ひと通り外部と内部を縫ってみました。
周りの畑の土の色と同じカラーになってしまいました。

とりあえず一回塗りです。余裕があればもう一回塗りたい所です。

屋根工事
そして屋根工事。下地は構造用合板なので合板の保護も兼ねてアスファルトルーフィングを貼りました。
これを貼る事でガルバリウム鋼板の波板も長持ちします。

波トタンをトタン釘で一本ずつ固定する地味な作業。



約一時間ほどで屋根葺き完了です。

鶏の産卵スペースを確保
内装工事に必要なものは、【産卵箱】と【止まり木】などでしょうか。
産卵箱は自宅で制作してきたものを現地で取付ました。
寸法は300×300×400(高さ)を一組としました。
多分15羽くらいなのでこれ位で足りるのかと思います。
計画としては産卵箱の下に水飲み場とすれは汚れが少なそうです。
その代わり産卵箱の上のスペースは塞がないと糞まみれになりそう。
今何かを考えています。

止まり木を付けて最後の仕上げ
止まり木を作るためにモクマオウの枝を伐採。
これを小屋の中に取付ます。

二人でちょこちょこ作業をしながらほぼ完成に近づいてます。

給餌器の設置や階段 そして最後に床を整えて耕します。




チャボを入れてみました
購入した有精卵を孵化器で温めているのですが孵る予定が4/6なのでまだまだ先になります。
それまで寂しいのでチャボを譲りうける為に二人で鶏を見に行きました。
大きな鶏には、ミナグ君もビビッてますが・・・




チャボを3羽貰ってきました。オス1羽にメスが2羽です。
まだ小さい子供のチャボです。



本日からみなぐ君の養鶏場のスタートとなりました。
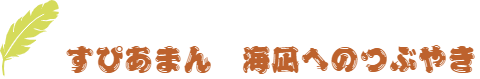



コメント